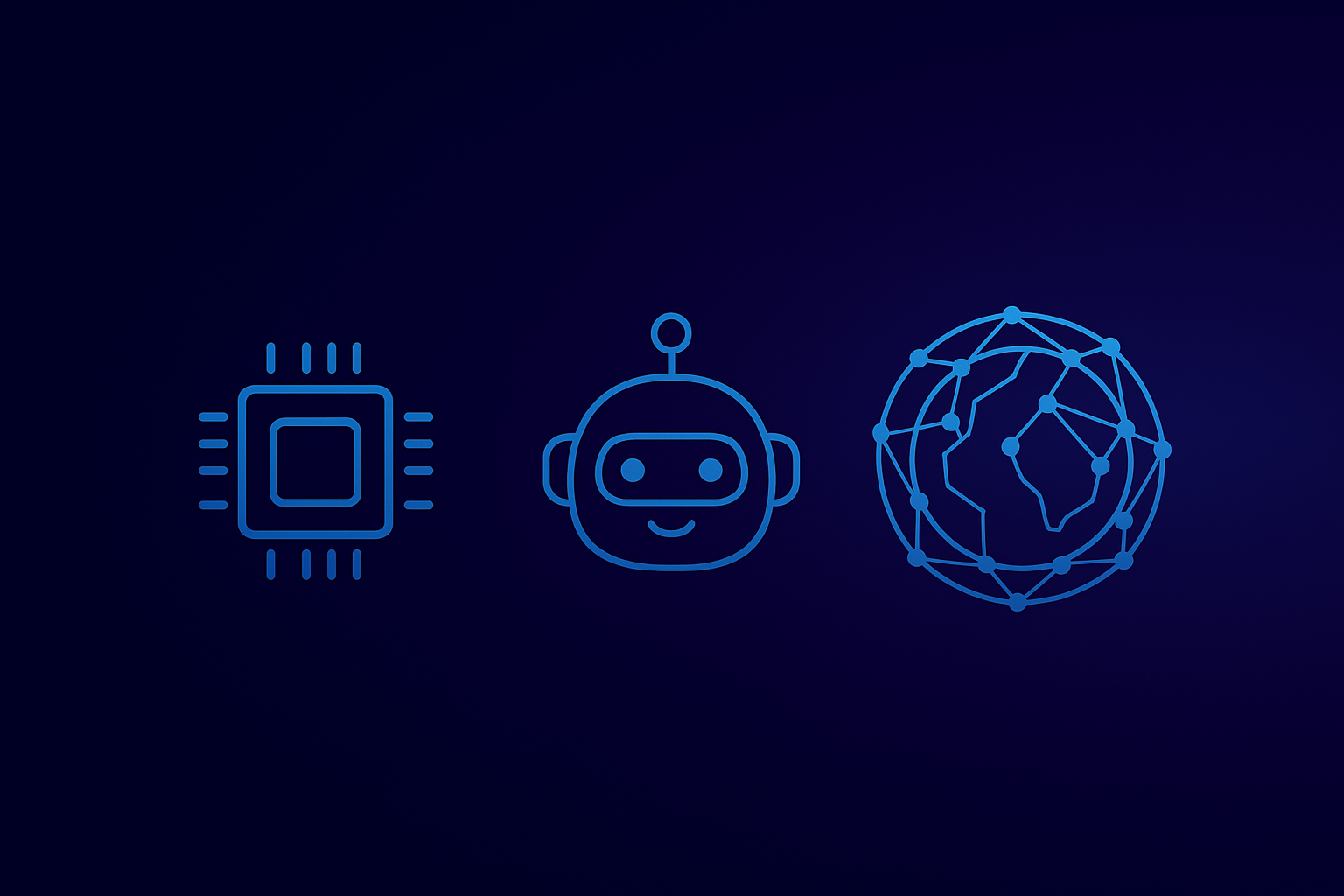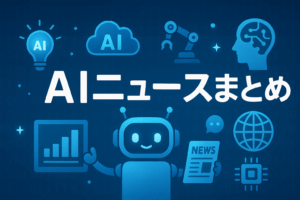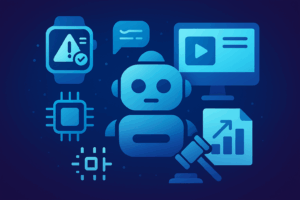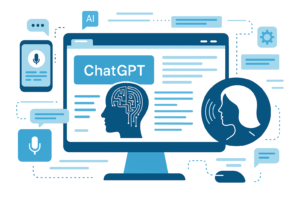生成AIの現場が再び熱を帯びている。NVIDIAは次世代GPUを公開し、中国は「国産AI」の自給自足に動き、そして日本ではついに文科省が教育現場への生成AI導入に本腰を入れ始めた。AIインフラ、社会実装、国際競争──今日の3本はその縮図。
目次
NVIDIA──次世代AIチップ「Rubin」発表でGPU戦争再加速
Google I/Oの直前タイミングで、NVIDIAが新アーキテクチャ「Rubin」とAIサーバーシステムを公開。2026年投入予定だが、今後のLLM開発者のGPU選定に大きく影響しそう。AIインフラの主導権を巡る戦いが、H100・B200からさらに次のフェーズへ。
▶ なぜ注目?
- Google、AWS、Metaなどのクラウド事業者がすでに「Rubin世代」の先行予約に動いている
- AIモデル開発は“どのGPUに最適化されているか”でパフォーマンス差が激変する世界
▶ 今後の展開予想
- 開発者側は今のうちから「Rubin対応LLM設計」を意識し始める必要あり
- 日本企業もデータセンター戦略や省電力対応を見直すタイミングが迫る
中国──小紅書、国産LLM「赤言」リリースで生成AIの“自立”を加速
SNS大手・小紅書が社内開発のLLM「赤言(RedLLM)」を発表。公開デモでは広告文生成や商品レコメンドに特化した軽量モデルを披露。百度、阿里巴巴に続き、非検索系IT企業も“自前の脳みそ”を持ち始めている。
▶ なぜ注目?
- 米国制裁で海外モデル/APIが制限される中、「自社LLMで事業を回す」構図が拡大
- 中国市場ではLLMを“検索”や“汎用”ではなく、業務特化型にチューニングする流れが主流化
▶ 今後の展開予想
- 中国発のLLMが商用サービス内に深く埋め込まれ、API提供ではなく裏側ロジックになる
- 日本でも「◯◯特化LLM」を自社開発する例が今後増える可能性
文部科学省──高校・大学で生成AI活用を明文化、教育現場に転機
文科省が新たな「生成AIの活用ガイドライン案」を発表。レポート作成支援や探究学習のヒント提供など、利用範囲を明示しながら積極活用を後押し。ついに“使ってはいけないもの”から“教育の道具”へと正式に立場を転換した。
▶ なぜ注目?
- 多くの学校が「黙認」状態だった生成AI活用が、国の方針で一気に“制度化”される流れ
- ChatGPT禁止といったローカルルールと衝突するケースも出そう
▶ 今後の展開予想
- 教育現場では「AIリテラシー+プロンプト設計」が必須スキル化する
- 私立中高やEdTech系スクールは先んじて“生成AI授業”をウリにし始めるかも